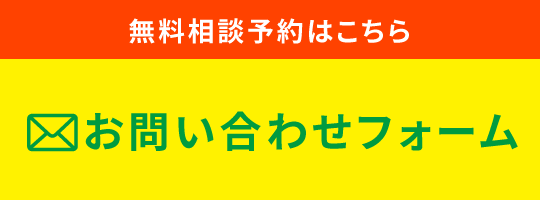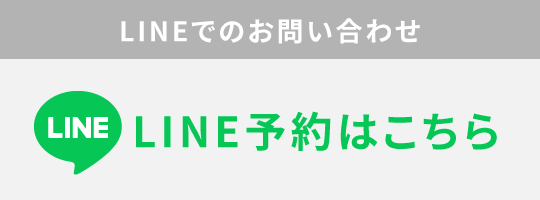常習賭博罪で有罪の確定判決を受けた者が、裁判中に開始した別の賭博行為により警察の取調べを受けた事件を参考に、常習賭博罪の成立や一事不再理効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡市在住の会社員男性Aは、2020年1月から同年12月までの間、オンラインカジノで度々金銭を賭けたとして、常習賭博罪で起訴され有罪となり、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、2021年6月に刑が確定しました。
Aは、裁判中の2021年4月頃から再びオンラインカジノを行うようになり、そのことが同年12月に警察に発覚し、同年4月から12月までの賭博行為について、警察の取調べを受けることとなりました。
(事例はフィクションです。)
常習賭博罪の成立について
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する、と定められているのに対し、常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処するとされ、賭博行為をした者に常習性が認められる場合に刑を加重しています(刑法第185条、186条)。
常習賭博における「常習」とは、反復・継続して賭博をする習癖のあることを意味し、判例によると、賭博行為の種類、賭けの金額、賭博行為が行われた期間・回数、同種前科の有無などの諸般の事情により総合的に判断されます。
常習性が認められる場合には、個々の賭博行為に賭博罪が成立するのではなく、常習賭博罪一罪が成立することにとなります。
一事不再理効について
本件Aは、2020年1月から同年12月までの間のオンラインカジノでの賭博行為により、常習賭博罪で懲役1年6月(執行猶予3年)の確定判決を受けていますが、当該賭博行為とは別の、2021年4月から同年12月までの間のオンラインカジノでの賭博行為について、別途罪に問われる可能性はあるのでしょうか。
何人も、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない、との憲法第39条の規定を受け、刑事訴訟法第337条で、既に確定判決を経た場合に再度起訴された場合、判決で免訴の言渡しをしなければならない、と定められています。
この規定は、一度有罪判決を受ける危険にさらされた者を同じ事実で再び危険にさらすべきではないという、「二重の危険」の考えに基づくものとされ、「一事不再理効」と呼ばれます。
ここで、「確定判決を経た」の範囲が問題となりますが、公判手続において、「公訴事実の同一性」の範囲で審判対象である訴因の変更が許され、有罪とされる危険が生じることから(刑事訴訟法第312条参照)、訴因の変更が許される「公訴事実の同一性」の範囲と「確定判決を経た」の範囲が通常重なると考えられます。
常習賭博罪は、常習性が発現された賭博者の一連の賭博行為を、1個の常習犯罪として処罰の対象とするものであり、本件Aが起訴され有罪の確定判決を受けた常習賭博罪の判決確定時までに反復して行われた賭博行為は全て、同裁判の「公訴事実の同一性」の範囲に含まれると考えられます。
よって、確定判決を受けた2021年6月より前に行っていた、2021年4月から同年6月までの賭博行為は、既に「確定判決を経た」場合にあたるとして、起訴された場合は免訴になる可能性が高いため、罪に問われる可能性は低いと考えられます。
他方で、2021年7月から同年12月までの賭博行為は、確定判決後に新たに行われているため、そもそも一事不再理効の問題とはならず、別途、賭博罪や常習賭博罪として罪に問われる可能性はあると考えられます。
賭博の容疑で取調べを受ける場合の弁護活動
賭博の容疑で逮捕されるなどして警察の取調べを受ける場合、賭けの金額、賭博行為が行われた期間・回数、などを中心に聴取され、常習性が認められると判断された場合には、容疑が常習賭博罪に変わる可能性があります。
また、警察の取調べで作成される供述調書は、検察官が処分を判断する際の重要な判断材料になるほか、起訴され裁判となった場合は、証拠となります。
そのため、意思に反した供述調書が作成されるなどして不利益を被らないよう、刑事事件の弁護活動の経験豊富な弁護士に、取調べ対応について事前に相談しておくことをお勧めします。
この他、弁護士は検察官と処分交渉を直接行うことも可能なため、弁護士に依頼することで、ギャンブル依存症の治療のため専門機関を受診していることや、二度と賭博を行わないことを誓約していることなど、被疑者に有利な事情を弁護士が検察官に申述することで、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることが期待できます。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件に強く、様々な刑事事件において不起訴処分を獲得した実績が数多くあります。
自身やご家族が賭博の容疑で警察の取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。